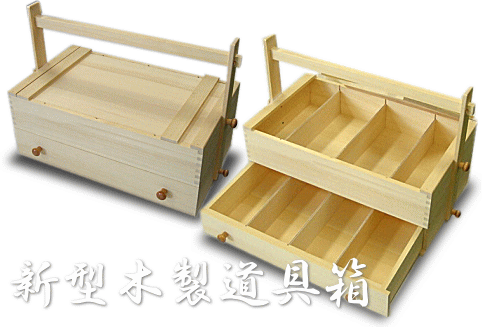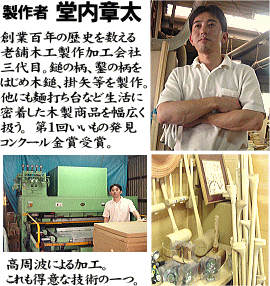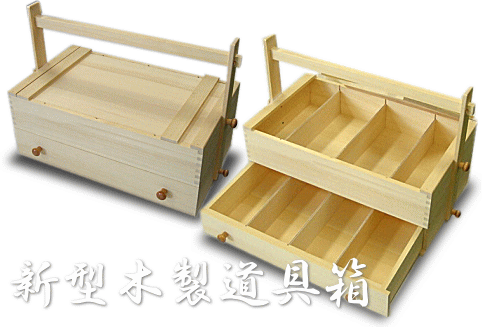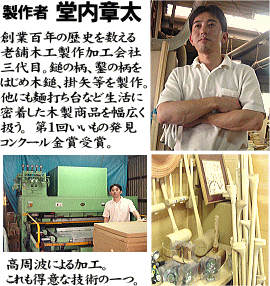|
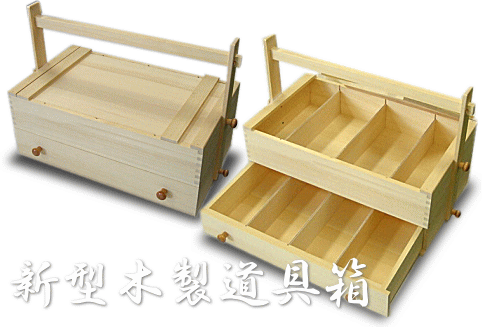 |
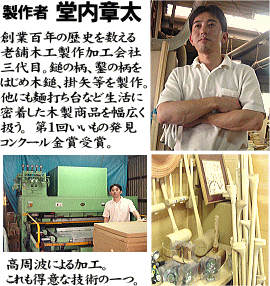 |
| ■木工のプロとしての拘りを随所に見せた『木製 左官道具箱』です。 |
 |
 |
| ■使用木材: |
高級鏝の柄と同じヒバ材を使用。水に強く、湿気の吸収に優れている。
更に今回は購入した材料を半年間寝かして板の変形を最小限に抑えた。
宮大工が作る祭りの屋台なども、このヒバ材が多用される。 |
| ■仕切り板: |
上下2段共に3枚の仕切り板を有する。 取り外しも簡単。 |
| ■底/天板: |
高周波圧着による合わせ板を使用。 平板より耐久性がありヒズミに強い。 |
| ■仕上げ: |
各面は正確にテーパー取りを行う、家具調仕上げ。 |
|
|
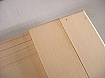 |
 |
| ■蓋の開閉: |
上蓋(うわぶた)を軽くスライドさせ、蓋を取り外す構造。実は前回の木製道具箱では、この
フタ部分の精度を上げ過ぎてしまい、湿度などの影響を受け、フタの開け閉めがキツクなり
過ぎる弱点があったが、今回は設計段階から改良を加えました。それでもグラ付きや
余分な隙間は最小限に抑えております。
|
|
|
 |
| ■箱 組: |
木工職人ならではの『石畳蟻継工法』。
ぐら付き、がた付きが無く、箱組には
理想の工法。
全ての面にテーパー面取が施されて
いる。 見た目も美しい。 |
|
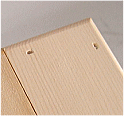 |
| ■釘 打: |
基本的には釘は使用しない。
極一部分のみ補強のために
極小の返し付きタップを採用。
殆ど目立たない。
|
|
|
| ■製品外寸 |
■製品内寸 |
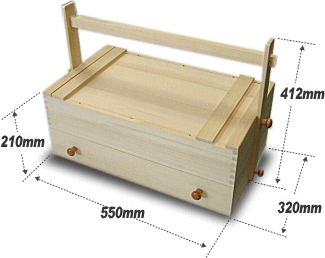 |
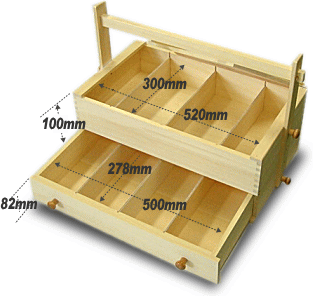 |
|
■「おかもち」スタイルの特徴は
持運びに便利なここと、作業時は
取っ手部分に鏝が掛けられること。 |
■更に、この道具箱の取っ手部分はネジ式で
取り外しが可能。高さも3段階で調整出来ます。
(注意)ネジは必ず片面2箇所で固定して下さい。 |
■取っ手をとり外せばシンプルな道具箱に
変身。 |
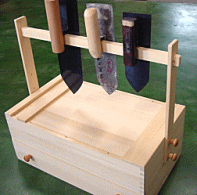 |
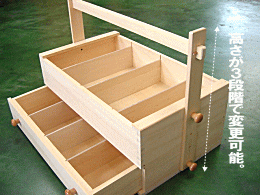 |
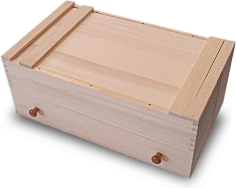 |
|
| ■取っ手部分の溝加工。 |
■ネジ式で固定します。 |
■カワイイ木製ネジ。 |
■細部にも職人技が光る。 |
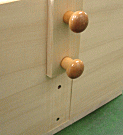 |
 |
 |
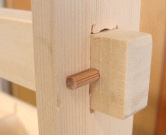 |
|
■下段の引き出し部分に施された数々の仕掛けです。 1枚目の赤印部分は固定の為に使われた、返しタップ。
クギを使わず、タップを使用しても見えないと言う気遣いが嬉しい。 箱組のようにキッチリと収まる引き出し部。
(注意)引き出し部分を取り出した場合、再び収める際は慎重に左右対象を意識し丁寧に収めて下さい。
高い精度で製作されているため、傾いた状態で無理に押し込むとトラブルの要因となります。 また、密閉度が
高く、万が一、空気がこもり、開け閉めが困難な場合は、上段の収納部分(引き出し部分からすれば天井部分)に
幾つかの空気穴を開けてやると開閉がスムーズになります。 |
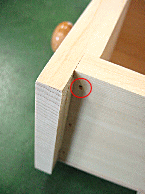 |
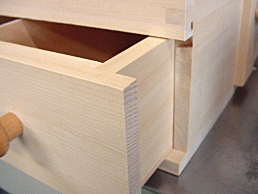 |
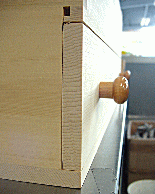 |
|
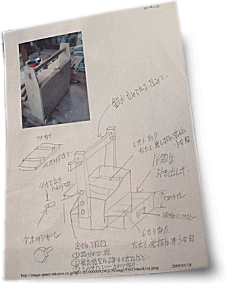 |
■[完成までの道のり]
初代道具箱の好評を受けながらも、私と堂内氏の心の中には、もっと皆さんを
驚かせたい。 そんな野心が沸き上がっていました。
事実、数々のブログや勉強会で見せられる手作りの道具箱の機能性は
私の想像を遥かに越えた素晴らしい作品ばかりだったからです。
幾つかの思案を繰り返しながら、私は左のヘタな絵でイメージを堂内氏に
伝えました。 そして、そこから更に、自信の持てる力で「凄いのにしてくれ!」と、
呆れる様な注文で製作を依頼しました。 勿論、予算もロッド数もお任せです。
そうで無いと、本当に良い物は生まれないからです。
対する堂内氏が切り出したのは時間をくれと言うことでした。
正直、それを聞いた時、私の無理に付き合うのも飽きたのかと不安を感じ
ました。 確かに日頃の仕事に一回限りの製品製作をはめ込むのは容易では
ありません。 そんな彼に恐る恐る、理由を聞くと彼の応えは「今度の作品では
前回の反省も踏まえ、材料をゆっくり寝かせたい」とのことだった。
|
「時間なんて幾らでも使ってくれ!」 私はハシャグ心を抑え、その時をただ待ちました。 そして1年が過ぎ、
ついに完成したのです。 ロッドは僅か9台。 取り寄せた材料から更に理想の木材を厳選すると作れた限界だった
そうです。 彼曰く、仕切り板以外は一切、合板は使用していない。
もう、文句の付けようがない、隅々までに職人芸が際立った素晴らしい作品です。 後は使う方が、その日常のなかで、
生きた汚れや日焼けが本物の風合いとなり、後世まで受け継がれて下されば幸いです。
商品名:新型木製道具 販売価格:37,800円(税込)★完売しました。 |
■お願い:本ロッドが完売しても、次のロッドの着手は困難です。 堂内氏によれば、手間作業が多過ぎるため、
一年に1回程度にして欲しい(笑)とのことなので、完売の節はご了承下さい。 (職人魂)
|
|
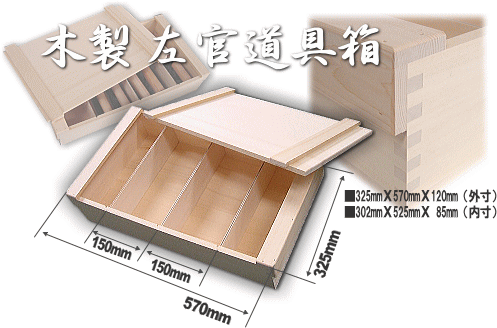 |
■記念のために旧型の道具箱の写真も残しておきました。
|
|