 |
■藤本さんに私達若造が
言うのも何ですが、本当に
上手くなったよね。
特にベテランの域にある中、
更にステップUPされている
所が凄いよ!
使い込む価値がある。
それが藤本さんの鏝やね。
|
|
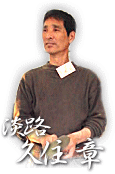 |
■藤本さんの鏝は大好きでね。
もう、これまで京都の2軒だけで
1,000万円ほど手に入れたね。
もう作ってないと聞いてたけど
無理をせず、これからも頑張って
欲しい。 使い始めは多少頑固
だけど馴染み始めたらこれほど
頼りになる鏝はない。
いざと言う時の鏝やね。
|
|
|
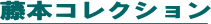 |
|
■下記商品は氏がこれまでに製作した鏝を
コレクションとして所有している品々です。
残念ながら、ご購入頂くことは出来ません。 |
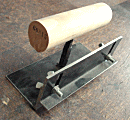 |
■段付面引鏝
※氏は多くの機械鏝を製作
している。 いずれも量産品
ではなく、技術試練のため
に製作している。
|
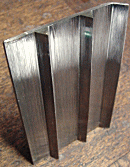 |
■ノンスリップ鏝Aタイプ
※高い精度と美しい仕上り
が絶品。
この様な鏝の製作は元来、
鏝鍛冶は手間の割りが合
わず好まない。
しかし氏はあえてチャレン
ジしている。 |
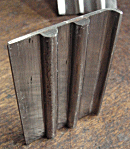 |
■ノンスリップ鏝Bタイプ
※これも左官職人の要望で
応えて製作した鏝。
丸棒を指定サイズで溶接し
成形している。
溶接も勿論、氏の手による。 |
 |
■ノンスリップ鏝Cタイプ
※アール角度やラインの
本数等、要望は多種多様。 |
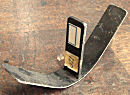 |
■京都茶室面引鏝
※京都のなじみ左官職人に
よるオーダー品。
製作には苦もなかったが
完成品には興味を抱いたと
言う。 |
 |
■ツブ引鏝
※古くから手掛けてきた鏝。
それだけに細部の拘りには
氏の究極の技が取り込まれ
ている。 勿論首も手作り。 |
 |
■サジ鏝色々
※当社のサジ鏝も氏の作品
。このコレクションが左官の
歴史を物語る。 |
 |
■引きずり鏝
※漆喰のパターン付け用鏝。
鎚による打ち出し品。
型を使わない手間の掛かっ
た逸品。今後も、製作する
予定はない。 |
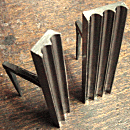 |
■ノンスリップ鏝Dタイプ
※削り出し工法により、完成
した鏝。 要望があっての製
作とは言え、ここまでやる
か。高い精度が伺える。 |
 |
■人造鋼ダルマ鏝
※鎚一本での叩き出し。
これこそが人造鏝。 |
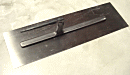 |
■本焼角鏝手カシメ仕上
※他の鏝鍛冶より、一早くに
角鏝を製作していた。もし
量産していたら凄いことに・・
|
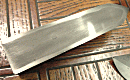 |
■フチ焼鏝
※その名の通り、地金の
フチ部分に、のみ焼入れを
施した鏝。
中央は地金の状態。
|
 |
■こなし鏝
※中央の厚みを生かすには
素材を痛めないこと・・・
見た目ではなく、実用目的の
こだわりは本物です。
|
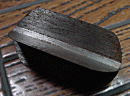 |
■本焼四つ羽根面引
※プラスチック製ではない
本物の四つ羽根。
極薄の板材と四面には
4サイズの面が正確にある。
|
 |
■人造元首四半鏝
※本鍛造品。四半鏝、本来
の形状こそがこれ。
首の取付けは勿論、カシメ。
|
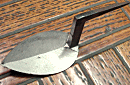 |
■元首柳刃御多福型鏝
※細部の仕上りが美しい。
当時の左官職人による拘り
が伺える。
軽くアールが入る。
|
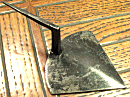 |
■本焼鋼黒磨砂切鏝
※やはり鍛造品。一枚の
鋼から打ち出し成形される。
肉厚のバランスが良い。
|
 |
■波丸面通し鏝
※用途としては不明。やはり
オーダーによる品。
指定サイズに半丸を製作し
溶接・磨きで完成している。
溶接跡を見せないのも氏の
こだわり。
|
 |
■煉瓦鏝
※これまで製作していたとは!
口金も自作品。鉄首も勿論
自作。形状も美しい。サイズは
3種類製作している。
|
 |
■チリ際磨き鏝
※近年に要望があり製作した
鏝。鍛造の首は美しい仕上り。
それ以上に押さえ圧が正確に
伝わる逸品は正に神業。
|
 |
■本鍛造玉鏝
首そして本体の仕上り等
生き生きとしている。
鍛造の魅力は使い込むことで
発揮される。
|
 |
■人造柳刃切付鏝
※鍛造そして打出しによる品。
一切の溶接を使用していない
究極の完成度。
氏の拘りが伺える逸品。
|
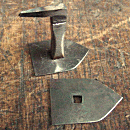 |
■アリ鏝一寸
※本体・首の全てが一点もの。
通常サイズより手間の掛かる
鏝。実用品としては最小の鏝。
オーダーした職人の遊び心が
伺える。
|
 |
■機械鏝(内角・外角)
※信じられないが全てが手
作業の逸品。 角度の変更も
可能。 実用性は別として
これも楽しんで作ったと言う。
|
 |
■貴帳面鏡面仕上鏝
※独特の形状をに加え、
鏝中央ラインを鏡の様に
磨き上げ仕上げている。
|
 |
■造園用叩き鏝
※左はオーダー品でとても
大きい。 右は通常品ながら
共に先端の形状に丸みがあ
る。もしや本来の形状も、
これが正しいのかも?
|
 |
■水捏ね撫で鏝
※鍛造・ヒズミ取り・そして
焼入れ。 細部の工程に生
きる氏の技が遺憾なく発揮
された名品。
|
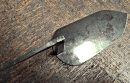 |
■鋼人造黒打柳刃鏝
※独特の形状は京仕上げ。
漆喰壁専用として左官職人
のオーダーとして製作され
た鏝。
|